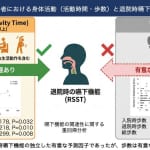2025/9/29公開 著者:小瀬英司 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 薬剤部)
はじめに
高齢者では、加齢に伴う薬物動態・薬力学の変化(腎機能や肝血流の低下、体水分量の減少と脂肪量の増加、中枢神経系の感受性亢進など)により、同じ用量でも薬物有害事象が生じやすくなります。併存疾患の多さや多剤併用、複数診療科・複数薬局の関与が重なると、処方の質を維持することは一段と難しくなります。本稿では、潜在的に不適切な薬剤(potentially inappropriate medications: PIMSs)の定義と背景、国内ガイドラインの位置づけ、代表的薬効群の要点を概説します。
PIMsの定義―「高齢者では薬物有害事象の発現リスクが利益を上回りやすい薬」
PIMsとは、一般成人では一定の有効性が期待できても、高齢者では安全性・有効性・代替選択肢の観点から相対的に不利益が大きくなりやすい薬剤を指します。適応と投与量が正しくても、転倒、せん妄、認知機能低下、電解質異常、出血、腎機能悪化などのリスクが増す状況では「潜在的に不適切」と判断され得ます。PIMsは、本来処方すべき薬剤が処方されていない状態(potential prescribing omission: PPO)と合わせて不適切処方(potentially inappropriate prescribing: PIP)として捉えられます。臨床では「減らすべき薬(PIMs)」と「本来開始すべき薬の未処方(PPO)」の両面をスクリーニングする姿勢が不可欠です。
日本老年医学会『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2025』1)の位置づけ
同ガイドラインは、PIMsやPPOのスクリーニングに国際的に広く参照される、Beers基準2)やSTOPP/START基準3)の考え方を踏まえつつ、国内の実臨床に適合する形で「特に慎重な投与を要する薬物」や「開始を考慮すべき薬物」を体系化しています。領域別に推奨の強さや根拠の質を明示し、腎機能に応じた用量調整、漫然投与の回避、相互作用の監視、服薬支援・情報共有の仕組み化まで、実装可能性を重視した記載が特徴です。外来・病棟・在宅のいずれでも、定期的な処方レビューと減薬を推進する際の拠り所となります。
代表的PIMsの領域別の要点
1. 中枢神経系薬剤
ベンゾジアゼピン系やZ-drugが転倒・せん妄・日中のふらつきを助長し、三環系抗うつ薬は強い抗コリン作用と起立性低血圧を介して機能低下や認知機能悪化を招きやすくなります。
2. 抗コリン作用を有する薬剤
抗コリン作用薬(第一世代抗ヒスタミン薬、過活動膀胱治療薬、パーキンソン病治療薬の一部など)は、便秘・尿閉・口渇・せん妄・認知機能低下を惹起しやすく、特に高齢者では薬剤性認知機能障害のリスクが強調されており、注意が必要です。
3. 鎮痛・消化器系薬
NSAIDsは消化管出血・腎機能悪化を増やします。PPIは適応のない長期連用で Clostridioides difficile感染症、低マグネシウム血症、骨折リスクの増加が指摘されており、適応・期間の見直しが求められます。
4. 循環器・内分泌代謝系薬
利尿薬は低ナトリウム血症や低カリウム血症を介して転倒・不整脈リスクを増やすため、定期的な電解質モニタリングが欠かせません。糖尿病治療薬の中でも特に長時間作用型スルホニル尿素薬は遷延性低血糖の原因となるため、高齢者では推奨されません。
5. 抗血小板薬の一次予防目的使用
近年のエビデンスでは、75歳以上の高齢者におけるアスピリンの一次予防効果は限定的であり、出血リスクが上回ると報告されています。そのため、高齢者へのルーチン投与は避けるべきとされています。
表1 代表的なPIMsの例
| 薬剤 カテゴリー | 代表的な薬剤 | 主なリスク | ガイドラインでの位置づけ |
|---|---|---|---|
| ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬 | ジアゼパム、フルラゼパム、 トリアゾラム、エチゾラムなど | 過鎮静、認知機能低下、 せん妄転倒、骨折、 運動機能低下 | 可能な限り使用控える(長時間作用型が使用回避)、 トリアゾラムは健忘のリスクがあり、使用回避 |
| 抗コリン作用薬 | 三環系抗うつ薬(アミノトリプチン、イミプラミンなど)、第一世代抗ヒスタミン薬、過活動膀胱治療薬(オキシブチニン) | 認知機能低下、便秘、尿閉、せん妄、口腔乾燥、便秘 | 可能な限り使用控える |
| NSAIDs | すべてのNSAIDs | 腎機能障害、上部消化 管出血 | 短期間の使用 |
| 長時間作用型 SU薬 | グリベンクラミド、 クロルプロパミド | 持続性低血糖 | 可能な限り使用控える。 代替え薬としてDPP-4阻害薬を考慮 |
| 抗血小板薬 (一次予防目的) | アスピリン | 出血リスク > 予防効果(高齢者) | 一次予防では非推奨 |
予後との関連
最近の前向きコホート研究4)では、Beers基準やSTOPP/START基準で定義されるPIMsの蓄積が全死亡リスクの上昇と関連することが示されています。地域在住高齢者1,210人を対象に、PIPは81.2%に認め、PIMsはBeers基準で 52.6%、STOPP基準で 45.0%、PPOは59.3%認められました。多変量解析では、PIMsが2剤以上で全死亡リスクが上昇(Beers基準;HR:1.3、STOPP基準;HR:1.3)、非がん死亡も約1.4倍に増加しました。PPOは用量反応的に死亡と関連し、2項目以上で全死亡1.8倍、非がん死亡2.0倍でした。交互作用として、PPOの影響は男性で強く、PIMsの影響は自己健康評価が良好な者で顕著でした。この研究ではPPOも生命予後の悪化と結びつく可能性が指摘されており、単に「薬を減らす」だけでなく、心血管二次予防に必要な薬や骨粗鬆症治療薬、ワクチンなど、患者のゴールに適う“足りない薬”を適切に開始する視点も重要です。
まとめ
PIMsは「高齢者で相対的に不利益が大きくなりやすい薬剤」を指す概念であり、Beers基準やSTOPP/START基準、ならびに日本老年医学会『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2025』を参照して体系的にスクリーニングし、処方の適正化を図ることが重要です。あわせて、必要な薬剤が開始されていない過小処方(PPO)も評価し、PIMsとPPOを包括した不適切処方(PIP)の枠組みで処方の質を高めることが必要です。最終的には、患者さんのゴール・オブ・ケアに即して、腎機能や相互作用、転倒・せん妄リスクを踏まえつつ、減らすべき薬は計画的に減らし、必要な薬は適切に開始するという両輪の介入を、定期的なフォローアップのもとで実践していくことが求められます。
引用文献
1) 日本老年医学会編集. 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2025.メジカルビュー社.
2) The 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023.71: 2052-2081.
3) O’Mahony D. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 3. Eur Geriatr Med. 2023. 14: 625-632.
4) Orenstein L. A Prospective Study on Potentially Inappropriate Drug Use and All-Cause Mortality in Community-Dwelling Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2025. Online ahead of print.
本記事は仲谷鈴代記念栄養改善活動振興基金の支援を受けています