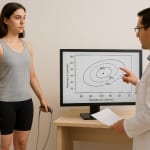2025/3/30公開 著者:前田圭介
はじめに
低栄養を診断する国際基準として、近年GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準が提唱されています。日本ではすでに診療報酬にも組み込まれましたのでGLIM基準を用いた低栄養診断が普及し始めました。GLIMでは表現型と病因という二つのカテゴリーを満たした場合に低栄養と診断します。表現型は体重減少、低BMI、筋量減少を含んでいます。筋量評価は、体組成分析機器の利用が奨められていますが、機器がなくても下腿周囲長や上腕周囲長などの簡便な身体計測でも評価することができます。本記事では、GLIM基準を実臨床に導入するために筋量評価の概要を整理し、とくに下腿周囲長測定の実践方法、カットオフ値、浮腫(むくみ)時の対応、BMI補正、そして筋量低下の重症度評価について解説します。
GLIM基準における筋量評価の概要
エキスパートグループであるGLIMは、筋量評価についてのガイダンス論文(1)を出版しています。その中には以下のように、筋量評価の多様性を示しています。
- 定量的評価:DEXA(二重エネルギーX線吸収法)、CT、BIA(生体インピーダンス)などが推奨されます。ただし、これらは高価または専門技術を要するため、日常診療では普及しにくいのが現状です。
- 身体計測と視診:リソースが限られる場合は、身体計測(anthropometric measures)や視触診でも筋量評価が可能であると指針は述べています。GLIMでは具体例としてCCやMUACが挙げられており、性別・人種特異的なカットオフ値の活用も推奨されています。
GLIMの最初の論文(2)では、筋力(握力など)を筋量の代理指標として用いる可能性にも言及されていました。しかし、その後のコンセンサス(1)では、筋力測定は筋量の代用には推奨されないと明言されました。筋力低下はサルコペニアの重要な要素ですが、筋量とは必ずしも比例しないためです。したがって、GLIM基準で低栄養診断を行う際は、筋量自体の評価を重視することになります。筋量の評価結果は、低栄養の重症度を判定する際にも利用されます。例えば筋量減少が著しい場合はGLIMの重度低栄養に該当し得ます。しかし、筋量評価の方法は多様ですので、著しい筋量減少をどのように判断するのか、議論をよんでいます。
下腿周囲長測定の重要性と概要
なぜCC測定か?
下腿周囲長は、低コストかつ簡便、非侵襲的に骨格筋量を推定できる指標として注目されています。下腿周囲長はさまざまな身体計測値の指標の中で最も全身の筋肉量減少を反映しやすいこと知られています。また、下腿周囲長はDXA法やBIA法による筋肉量と相関が高く、サルコペニアのスクリーニングにも有用とされています。従って、特別な機器を用いることが困難な状況では、下腿周囲長を筋量評価の指標の第一選択と考えるべきだといえます。
GLIM基準とCC
GLIMの公式ガイダンス論文(1)でも下腿周囲長含む身体計測値を現実的な筋量評価の代替手段として認めています。実際、同論文(1)ではの下腿周囲長の世界共通カットオフ値が例示されており、男性33cm未満・女性32cm未満が筋量低下の目安として合意されています。これらの値は、主にアジア人や欧米人の研究から得られたエビデンスと専門家の合意に基づくものです。注意すべき点は、このカットオフ値の根拠は健康的または地域在住成人の研究から得られて値であり、病院のセッティングで妥当かどうかは未だ不明であることと、肥満(皮下脂肪が厚い)や浮腫の影響を受けることです。
下腿周囲長の正しい測定手順
CC測定の精度を高めるため、正しい手順と留意点を押さえましょう。以下に具体的なステップを示します。
- 姿勢の決定:患者さんの状態に応じて測定姿勢を決めます。可能なら立位が望ましいですが、立位困難な場合は座位(膝関節を90度)か仰臥位でも構いません。立位測定は座位よりやや小さめの値になる傾向があり(座位は約0.7cm大きい)と報告されています。したがって、一貫した体位での測定が重要です。ベッド上で臥位の場合は、膝を約90度に屈曲させ測定します。
- 筋肉のリラックス:両足を肩幅に開き、足を自然に床に接地させます(座位・立位共通)。ふくらはぎの筋肉が緊張しないように力を抜いてもらいましょう。衣類は膝下をしっかり露出させふくらはぎを露出し、測定箇所にメジャーが直接触れるようにします。
- 最大周囲の測定:メジャーを用いて、ふくらはぎの最も太い部分(最大周径)を探します。メジャーを軽く当てながら上下に動かし、一番大きくなる位置を確認します。この際、皮下脂肪を圧迫しすぎないように注意します。きつく締め付けず、皮膚に沿って密着させるのがコツです。1mm(0.1cm)単位まで読取ります。

測定上の留意点:
- 巻尺の選択:伸縮しない裁縫用の巻尺や専用のMUACテープを使用します。ゴム製で伸びるものは誤差の原因となります。
- 足の状態:立位では、両足に均等に体重をかけるよう声掛けします。座位・臥位では膝を直角に曲げ、ふくらはぎに緊張が入らない角度を確保します。
- 実施環境:患者さんがリラックスできる環境で測定しましょう。寒冷下では筋肉が収縮しやすいため、室温にも気を配るとベターです。
CC測定の推奨カットオフ値とその根拠
GLIMコンセンサスのカットオフ値
GLIMでは、CCのカットオフ値として以下の数値を提示しています:
- 男性: <33 cm
- 女性: <32 cm
これらは「低筋量の疑い」を示す目安です。実際には、対象集団によってカットオフは微調整されています。例えば、高齢入院患者の下腿周囲長でBIA法で得た四肢骨格筋量減少を同定する最適なカットオフ値は男性: ≦30cm、女性: ≦29cmでした(3)。このカットオフ値を適用してGLIM基準で低栄養診断をした観察研究ではその妥当性が示されています(4)。カットオフ値はあくまで目安であり、患者の年齢や疾患、人種によって調整が必要な場合があります。後述のBMI補正や浮腫補正も踏まえ、総合的判断を行いましょう。
下腿浮腫がある場合の対応
浮腫が筋量評価に与える影響
むくみ(浮腫)は、原因は多様ですが水分貯留による患部の腫脹であり、下腿周囲長測定値を過度に大きくしてしまいます。特に下腿浮腫があると、実際の筋肉量に比して2cm程度大きく測定される可能性があることが研究で示されています。例えば、Ishidaらの報告では、下腿浮腫がある高齢者では平均で男性約2.0cm、女性約1.6cm下腿周囲長が増加していたとされています(5)。
浮腫時の測定戦略
下腿に強い浮腫がある場合、1)男性2.0cm,女性1.6cmを引いた値を用いる、2)上腕周囲長の測定を用いる、3)臨床栄養の専門家による身体診察による判断を用いるという選択肢が考えられます。GLIMガイダンスでも「下肢に浮腫があり上肢にない場合、上腕周囲長を優先する」と述べています(1)。上腕周囲長はふくらはぎより浮腫の影響を受けにくい利点がありますが、全身性の浮腫がある場合はMUACも影響を受けますし、下腿周囲長に比べ全身の筋量の反映度が低下しますので、総合的判断が大切です。
臨床栄養の専門家が行う栄養アセスメントの1項目として身体診察があります。身体診察は筋量評価、浮腫や皮膚の状態、体液貯留の評価などが含まれます。知識と経験を積んだ専門家が主観的に判断する筋量評価は筋量評価の手法として妥当であるとされています。また、血液検査で筋量減少を評価することはできませんので、ご留意ください。
BMIが高い場合の補正方法(肥満時)
肥満と筋量評価
BMI(body mass index: 体格指数)が高い、つまり過体重や肥満の人では、下腿周囲長測定値が筋肉量の実態より高めに出ることがあります。それは、脂肪組織がふくらはぎを厚くしているためです。GLIMガイダンス論文(1)でも「肥満者では下腿周囲長カットオフが肥満でない人に比べ精度が落ちる」ため補正することを奨めています。一般的な補正方法として、一定の値を引きます。肥満度に応じた補正値として「BMI 25〜30kg/m2の人の場合3cm、BMI 30〜40kg/m2で7cm」を引くことが推奨されています。BMI 40以上では-12cmを測定値から引きます。
BMI補正の根拠
これらの補正幅は、NHANESデータなどからBMIとCCの関係を分析した結果に基づきます。BMIが高い集団では同じ筋肉量でもCCが太くなる傾向があるため、ある程度の目安値として補正するのです。ただし、補正後の値もあくまで参考値であり、患者の全身状態と照らし合わせた解釈が大切です。
注意点:BMI補正は、単にBMI値だけでなく、体脂肪率やむくみの有無とも関連します。肥満でも浮腫が強い場合は、肥満補正と浮腫補正の両方を適用することも検討しますが、二重補正による過剰な筋量低下判定にならないよう、慎重に評価しましょう。
重症度評価における筋量減少の考え方
GLIM基準では、低栄養と診断された場合に中等度低栄養か重度低栄養に重症度分類を行います。重症度分類では表現型に含まれる体重減少率、低BMI、筋量減少のいずれかが過度に(著しく)悪いことで重度低栄養と診断するものです。筋量減少は体重減少率やBMIと異なり評価手法が多様です。そのため、一律の評価方法と重症判断基準があるわけではありません。臨床栄養の専門家が身体診察の結果主観的に判断する過度の筋量減少という判断は尊重されるべきだと思います。専門家でない場合、過度の筋量減少をどのように考えるか迷うところです。
愛知医科大学では、下腿周囲長を用いて重症度判断をする場合、適用した下腿周囲長減少のカットオフ値の10%低い値を過度の筋量減少の判断基準と暫定的に考え運用し、GLIM基準の重症度判断が妥当であることを報告しています(4)。また、同様に、BIA法で得た四肢骨格筋量にも適用した嚥下障害の研究では、過度の筋量減少(サルコペニア診断基準のカットオフ値のさらにマイナス10%)により嚥下障害の有病率が急増したことも報告されています(6)。今後、過度の筋量減少をどのように考えるか、コンセンサスを形成する必要があると考えられます。
参考文献
- Barazzoni R, et al. Guidance for assessment of the muscle mass phenotypic criterion for the Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) diagnosis of malnutrition. Clin Nutr. 2022 Jun;41(6):1425-1433.
- Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9.
- Maeda K, et al. Predictive Accuracy of Calf Circumference Measurements to Detect Decreased Skeletal Muscle Mass and European Society for Clinical Nutrition and Metabolism-Defined Malnutrition in Hospitalized Older Patients. Ann Nutr Metab. 2017;71(1-2):10-15.
- Mori N, et al. Prognostic implications of the global leadership initiative on malnutrition criteria as a routine assessment modality for malnutrition in hospitalized patients at a university hospital. Clin Nutr. 2023 Feb;42(2):166-172.
- Ishida Y, et al. Impact of edema on length of calf circumference in older adults. Geriatr Gerontol Int. 2019 Oct;19(10):993-998.
- Nagano A, et al. Association of Sarcopenic Dysphagia with Underlying Sarcopenia Following Hip Fracture Surgery in Older Women. Nutrients. 2020 May 10;12(5):1365.