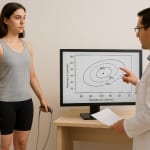2025/3/29公開 著者:森 直治
近年、血清アルブミン値は従来のような栄養指標ではなく、炎症マーカーとして捉えるべきであるという認識が広まりつつある。また、アルブミン値は臨床アウトカムとの関連が強く、予後予測因子やリスク指標としても用いられている。このような考え方は、令和6年度の診療報酬改定にも反映され、アルブミン値が栄養評価項目から除外されることとなった。長年、栄養状態を評価する上で中心的な役割を担ってきたアルブミン値が、その座を降りたことに戸惑いを覚える医療従事者も少なくない。そこで本稿では、アルブミン値を炎症マーカーとして捉えるべき背景について論じる。
まず、栄養指標とは何かを再確認したい。栄養ケアの目的は、体タンパク量を適正に保ち、生理的機能を維持することにある。しかし、体タンパク量を直接測定することは容易ではない。そのため、体重や体格指数(BMI)、近年では骨格筋量や筋肉の質といった代替指標が用いられるようになってきた。その中で、アルブミンは血清中に存在する主要なタンパク質であり、体タンパク量を反映すると考えられ、長く栄養指標として活用されてきた。
しかしながら、アルブミン値は体タンパク量が減少していない状況でも、急激に低下することがある。これは炎症によって血管透過性が亢進し、通常は血管外に漏出しないアルブミンが血管外へ移行するためである。筆者は米国留学中、筋肉の虚血再灌流モデルにおいて、炎症誘導後の再灌流により血管透過性が亢進し、アルブミンが血管外へ漏出する様子を生体顕微鏡下で観察した経験がある。アルブミンは分子量が大きく、通常は血管内にとどまるが、炎症が加わることでそのバリア機能が破綻し、漏出しやすくなる。
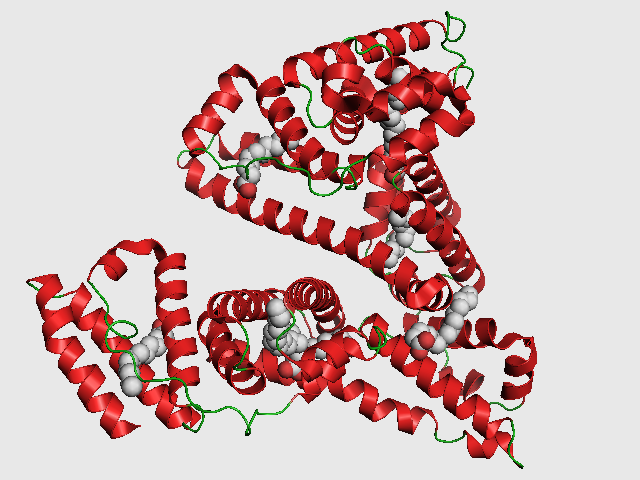
このような炎症反応によるアルブミン値の急激な低下は、臨床現場でもしばしば観察される。たとえば、交通外傷などで救急搬送された栄養状態良好な若年患者がICUに入室後、数時間以内にアルブミン値が半減することがある。これは体タンパク量が急激に失われたのではなく、炎症によって血管透過性が亢進し、アルブミンが血管外へ漏出した結果である。すなわち、アルブミン値は栄養状態そのものよりも、炎症の影響を強く受ける指標である。
アルブミン値の低下は、他にも肝機能低下による蛋白合成の減少、あるいはネフローゼ症候群における喪失量の増加といった病態でも認められる。とはいえ、近年の知見では、蛋白合成が必要とされる状態においては、肝不全を除き、肝臓の蛋白合成能はむしろ亢進していることが報告されている。このように、アルブミン値の解釈には多角的な病態の把握が必要となる。
一方で、明らかな低栄養状態であっても、炎症を伴わなければアルブミン値が著しく低下しないケースもある。たとえば、神経性食思不振症の患者や、古典的なマラスムスでは、重度の低栄養状態にもかかわらず、アルブミン値が比較的保たれていることが知られている。また、がんによる著明な体重減少があっても、進行がんに至り、炎症や体液貯留が顕在化するまではアルブミン値が保たれている例も少なくない。このことからも、アルブミン値が体タンパク量を一定程度反映する可能性はあるものの、それ以上に炎症の影響を強く受けて変動することが明らかである。
しばしば「CRPが正常であれば、低アルブミンは低栄養を示すのではないか」との質問を受ける。しかし、CRPが正常であっても、血管透過性が亢進している状態や、他の炎症性反応が存在している可能性は排除できない。CRPは炎症の一指標に過ぎず、炎症の有無をすべて判断できるわけではない。したがって、CRPとアルブミンの両者を併せて評価しても、必ずしも栄養状態を正確に反映するとは限らない。むしろ、アルブミンはCRPとは異なる側面から炎症を捉える指標として活用できる可能性がある。
以上のように、アルブミン値は血管透過性の変化によって短期間に大きく変動しやすく、栄養評価の単独指標として用いるには限界がある。一定の条件下では体タンパク量を反映する可能性が否定できないものの、炎症の影響を受けやすいため、その解釈には常に慎重さが求められる。現在では、アルブミン値はむしろ、炎症状態を鋭敏に反映するマーカーとして再評価されるべき指標であると考えられる。