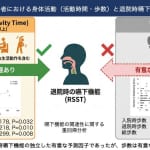2025/9/22公開 著者:宮原周三 (国立長寿医療研究センター老年内科)
高齢者医療では、疾患だけでなく、身体機能、心理状態、社会的側面を含めた多面的な視点が求められます。口腔の健康に関しても、う蝕(虫歯)や歯周病といった「疾患」に加えて、咀嚼、嚥下、発音といった「機能」が重要な評価対象として認識されるようになってきました。栄養は高齢者の健康を維持する上で欠かせない柱ですが、栄養摂取を支えるうえで口腔は重要な役割を担っています。こうした口腔機能を評価する代表的な指標として、「オーラルフレイル」と「口腔機能低下症」が挙げられます。本稿では、両者の概念や臨床的意義を中心に、栄養との関連を概説します。
「オーラルフレイル」の概念は、2014 年に初めて提唱されました [1]。2018年に、田中らにより診断基準が提示され、その基準で診断されたオーラルフレイルが身体的フレイル、要介護状態、死亡の独立したリスク因子であることが報告されました(表1)[2]。その後、オーラルフレイルに関する研究は国内外で広がりをみせました。
表1 オーラルフレイルの人が抱えるリスク
| 新規発症 | 新規発症 |
|---|---|
| 身体的フレイル | 2.4倍 |
| サルコペニア | 2.1倍 |
| 要介護認定 | 2.4倍 |
| 死亡 | 2.1倍 |
なお、留意すべき点として、国際的に使用される oral frailty と、国内で用いられている「オーラルフレイル」が必ずしも同一の概念ではないということです。これはFrailty と「フレイル」の関係に類似しており、研究や臨床の場では両者の違いを踏まえて理解・活用することが重要です。
oral frailtyについて、国際的に統一された定義や診断基準は現時点では存在していません。2022年にParisiusらは、oral frailtyの定義が7種類、さらに類似概念の定義が10種類存在することを報告しました [3]。これらoral frailtyの7件の定義を分析した結果、明確な違いが存在し、概念的一貫性を欠いていると結論付けています。診断基準については、2018年の田中らの報告が世界的にも最も広く用いられてきたものの、研究により様々な基準が用いられており、評価の一貫性に課題があることが指摘されていました。このような背景から、2023年には国際的な実用的基準(operational definition)の策定に向けた議論が開始されましたが[4]、2025年9月時点では、確立には至っていません。
日本国内では、「オーラルフレイル」の概念の明確化と普及を目的として、日本老年医学会、日本老年歯科医学会、日本サルコペニア・フレイル学会による 「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント」が2024年に発表されました [5]。このステートメントでは、オーラルフレイルの概念は「口の機能の健常な状態(いわゆる『健口』)と『口の機能低下』との間にある状態」と位置付けられ、その定義は「歯の喪失や食べること,話すことに代表されるさまざまな機能の『軽微な衰え』 が重複し,口の機能低下の危険性が増加しているが,改善も可能な状態」と示しています。
さらに、評価方法として、「Oral frailty 5-item Checklist (OF-5)」が提唱されました(表2)。OF-5は5つの質問項目から構成され、自己記入式で評価が可能です。そのため、歯科専門職が不在の場でも実施でき、地域住民から医療・介護の現場まで幅広い場面での活用が可能です。こうした簡便な評価法の導入により、早期段階から口腔機能の「軽微な衰え」に気づく契機となることが期待されます。
表2 Oral frailty 5-item Checklist:OF-5
| 質問 | 該当 | 非該当 |
|---|---|---|
| 1 自分の歯は何本ありますか? | 0-19本 | 20本以上 |
| 2 半年前と比べて固いものが食べにくくなりましたか? | はい | いいえ |
| 3 お茶や汁物等でむせることがありますか? | はい | いいえ |
| 4 口の渇きが気になりますか? | はい | いいえ |
| 5 普段の会話で,言葉をはっきりと発音できないことがありますか? | はい | いいえ |
| 2つ以上該当→オーラルフレイル | ||
当初の国際的な報告では、OF-5には一部専用機器を用いた評価が含まれていました[6]。しかし、その後、機器評価と自覚症状との妥当性を検証した論文が報告され[7]、合同ステートメントでは、最終的にすべて自己評価形式として提示されました。
「口腔機能低下症(oral hypofunction, OHF)」は、日本老年歯科医学会により 2016 年に提唱された概念であり、高齢者における口腔機能低下のリスクを軽減するための診断基準および管理戦略として位置づけられています[8, 9]。OHFは、口腔衛生、口腔乾燥、咬合力、舌口唇運動機能、舌圧、咀嚼機能、嚥下機能の 7 項目を評価し、そのうち3項目以上に低下が認められた場合に診断されます。評価は一部自覚症状に依存しますが、多くは専門的な機器を用いた客観的測定に基づきます。この点は、自覚症状を評価するOF-5と大きく異なります。OHFは、口腔の状態や機能を専門的かつ包括的に評価できる一方で、専門機器や専門知識を必要とするため、地域レベルなどでの実施には一定の制約があります。
オーラルフレイルと口腔機能低下症(OHF)の関係については、2016年の文書では、オーラルフレイルが悪化するとOHFに移行すると考えられていました[9]。しかし、現在では、両者をこのような重症度の違いとして捉えることは難しいとされています[10]。オーラルフレイルとOHFの一致率は約70%だったとの報告があります[11]。この知見は、両指標が部分的に重なりつつも異なる特徴を有していることを示唆しています。両者の適した実施場所は先述の通りですが、これらで診断されることの意義や全身的機能との関連、両者の関係性については今後も重要な検討課題です。
口腔の健康と栄養との関連については、これまでにも多くの報告があります。例えば、歯数の少ない高齢者では食の多様性が低下しており[12]、たんぱく質やビタミン類の摂取量が有意に少ないことが示されています[13]。また、十分な咬合力を有することが、たんぱく質、ビタミン群、食物繊維等の摂取量の維持に寄与していることも報告されています[14]。さらに、オーラルフレイルは食事の多様性を低下させ、それが身体的フレイルに繋がることが示されています[15]。栄養は高齢者の健康を支える不可欠な要素であり、その維持のためには口腔機能の適切な評価と早期に問題把握、介入が求められます。
本項では、栄養と深く関わる口腔機能について概説しました。口腔の健康を守ることは、栄養状態を含めた全体的な健康の基盤となります。OF-5によるオーラルフレイルの評価は、質問票で簡便に実施でき、スクリーニングとして有用です。しかし、機能低下の背景にある原因までを評価・特定することはできません。そのため、歯科による専門的な診察は不可欠です。例えば、う蝕や歯周病などの疾患による機能低下であれば、補綴治療や歯周治療により改善が期待されます。原因を見極めずに、機能改善を目指しても十分な成果は得られないため、疾患への適切なケアと併せて実施することが重要です。OF-5は歯科診療へつなげるための有用なツールであり、こうした評価を活用しつつ多職種による包括的な支援体制を構築することが、高齢者の栄養・健康を支える上で不可欠です。
【Reference】
1.国立長寿医療研究センター:平成25年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「食(栄養)および口腔 機能に着目した加齢症候群の概念の確立と介護予防 (虚弱化予防)から要介護状態に至る口腔ケアの包括的対策の構築に関する研究」報告書,2014.
2.Tanaka T, Takahashi K, Hirano H, et al. Oral frailty as a risk factor for physical frailty and mortality in community-dwelling elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018;73(12):1661-1667.
3.Parisius KGH, Wartewig E, Schoonmade LJ, Aarab G, Gobbens R, Lobbezoo F. Oral frailty dissected and conceptualized: A scoping review. Arch Gerontol Geriatr. 2022;100:104653.
4.Parisius KGH, Verhoeff MC, Lobbezoo F, et al. Towards an operational definition of oral frailty: A e-Delphi study. Arch Gerontol Geriatr. 2024;117:105181.
5.日本老年医学会,日本老年歯科医学会,日本サルコペニア・フレイル学会.オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント(Consensus Statement on Oral Frailty).老年歯学.2024;38(4):410?414.
6.Tanaka T, Hirano H, Ikebe K, et al. Oral frailty five-item checklist to predict adverse health outcomes in community-dwelling older adults: A Kashiwa cohort study. Geriatr Gerontol Int. 2023;23(9):651-659.
7.Iwasaki M, Shirobe M, Motokawa K, et al. Validation of self-reported articulatory oral motor skill against objectively measured repetitive articulatory rate in community-dwelling older Japanese adults: The Otassha Study. Geriatr Gerontol Int. 2023;23(10):729-735.
8.Minakuchi S, Tsuga K, Ikebe K, et al. Oral hypofunction in the older population: Position paper of the Japanese Society of Gerodontology in 2016. Gerodontology. 2018;35:317-324.
9.水口俊介, 津賀一弘, 池邉一典, 他. 高齢期における口腔機能低下─学会見解論文 2016年度版─. 老年歯学. 2016;31:81-99.
10.池邉一典,岩崎正則,上田 貴之, 他.口腔機能低下症の現在地:2023年度 口腔機能低下症ワーキンググループ 成果報告.老年歯学.2024;39(2):178-186.
11.Miyahara S, Maeda K, Kawamura K, et al. Concordance in oral frailty five-item checklist and oral hypofunction: Examining their respective characteristics. Arch Gerontol Geriatr. 2024;118:105305.
12.Iwasaki M, Kimura Y, Yoshihara A, et al. Association between dental status and food diversity among older Japanese. Community Dent Health. 2015;32(2):104-110.
13.Yoshihara A, Watanabe R, Nishimuta M, Hanada N, Miyazaki H. The relationship between dietary intake and the number of teeth in elderly Japanese subjects. Gerodontology. 2005;22(4):211-218.
14.Iwasaki M, Yoshihara A, Ogawa H, et al. Longitudinal association of dentition status with dietary intake in Japanese adults aged 75 to 80 years. J Oral Rehabil. 2016;43(10):737-744.
15.Iwasaki M, Shirobe M, Motokawa K, et al. Prevalence of oral frailty and its association with dietary variety, social engagement, and physical frailty: Results from the Oral Frailty 5-Item Checklist. Geriatr Gerontol Int. 2024;24(4):371-377.
本記事は仲谷鈴代記念栄養改善活動振興基金の支援を受けています