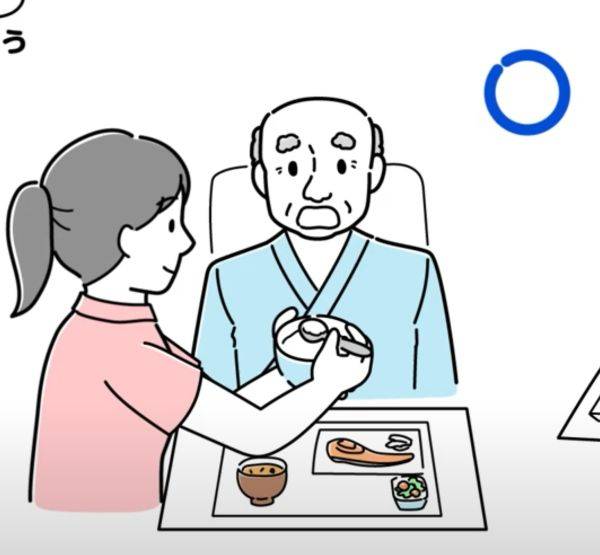図をクリックすると嚥下調整食写真ギャラリーへ移動します
おいしい嚥下調整食(嚥下食)
安全に飲み込みやすいだけでなく、「おいしい」と感じられることが理想です。
ところが、ピューレ化や刻みなどの加工をすると味・香り・見た目が弱まりやすく、満足度が低下しがちであることが報告されています。
安全性を支えつつ、おいしさの多因子要素を積み上げる発想が「おいしい嚥下食」には重要になると考えられます。
六感+メタ認知
味だけでなく、すべての感覚の統合と食物認知の最適化で「おいしい」と感じます
味覚・嗅覚
味は舌だけでなく、においでも修飾されるものです。高齢者では味覚・嗅覚しきい値が上昇し感覚・好みが変化するため、だし・スパイス・酸味で輪郭を強調すると摂取量が増えるかもしれません。
温覚
温かい料理は≥60℃、冷たい料理は≤10℃をキープすると風味強度が上がります。また、温度の感覚刺激は嚥下反射も促通されるかもしれません。
視覚
皿の色コントラストや食材を分けて盛ることで食物認知を最適化し摂取量が増えることが期待されます。
聴覚
静かな環境は”食事に集中”でき、咀嚼音が味覚強度を上げる可能性あり。一方で、食事中であることが分かる声掛けも一定の聴覚作用があります。
触覚
食具を持つ、触ることで食環境を認知しやすくなります。
姿勢
足底が地面についていることや、軽くした向き(あご引き)体位であることなどで安全に食することができる安心感を感じます。
食形態
安全性、効率性と喉越しを両立する粒度・粘度設定が要。咀嚼・食塊形成ができる人にはもぐもぐしながら食べる最適な食形態を検討します。
美味しい嚥下調整食をつくる7つのアプローチ
-
香りとコクを底上げ
だし、ハーブ、発酵調味料で”第4~5味覚”を活用。 -
温度マネジメント
保温・保冷食器で適温を保ち、香り立ちと嚥下促通を両得。 -
彩り
食材と食器の配色に配慮。食材の盛り方、ソースのかけ方に気配り。 -
音環境のデザイン
TVの消音、食事にあったBGMを”聴かせる”演出。食事場面であることの理解。 -
食具と姿勢
嚥下しやすい姿勢づくりに配慮。スプーンは浅め・柄太で触覚入力を増強。 -
“食前エクササイズ”と空腹づくり
軽い手足運動や嚥下体操で自律神経を賦活し、味覚感度を高める!? -
想い出の味を再現
ご当地の食文化を再現。文化的・情動的充足を誘発。
おいしい嚥下調整食を目指して
食形態の調整が必要な方にとって嚥下調整食(物性調整)は必要不可欠です。 しかし、物性調整すればよいというものではなく、おいしく食べていただくその下層を支えるのは多因子・多感覚・心理社会的な”おいしさの基盤”です。 医療・介護・給食現場では、「形態調整+五感強化+環境調整」をワンパッケージで提供することが、患者さんのQOL向上と栄養状態改善の鍵になります。
“おいしい嚥下調整食”は、栄養と安全と感動を同時に届けるケアテクノロジー。
私たち作り手・支援者こそが、その全てをデザインできます。
嚥下調整食を栄養強化する意義
摂食嚥下障害のある方は、エネルギーやたんぱく質の摂取が不足しやすく、筋肉量や体重が減少して低栄養が悪化するリスクがあります。
嚥下調整食は、単に「食べやすい」だけでなく、摂食嚥下リハビリテーションの一環としての役割を担いながら、必要な栄養素を安全かつ効果的に補給する手段でもあります。さらに、食事は”生きる楽しみ”の一つであり、「美味しく食べられること」も、心身の健康に大きく関与しています。しかし、嚥下調整食は調理時に加水が多く、栄養密度が低下し、栄養価が低くなりやすいという課題があります。そのため、意識的に栄養を強化する工夫が欠かせません。こうした工夫により、安全性と栄養の両立が可能になり、高齢者の健康維持と生活の質の向上に貢献します。
嚥下調整食を栄養強化することでADLの改善を期待できることが報じられています。
管理栄養士さんからの声
現場で活躍する管理栄養士が、日々の食事づくりで大切にしている工夫や想いについて語ります。
少量でも、エネルギーは満タンに
効率的にエネルギーを摂取できるよう、MCTオイル(中鎖脂肪酸油)やバター、マヨネーズといった脂質の多い調味料や油脂を調理に活用しています。
たんぱく質で、動ける身体づくり
筋肉や細胞を作るたんぱく質が不足しないよう工夫しています。たんぱく質パウダーを添加したり、豆腐、魚のすり身、卵、ヨーグルトなど、たんぱく質が豊富な食品をつなぎとして使用します。
素材の栄養を、一滴まで大切に
調理の際に加える水分をできるだけ少なくすることで、食材が本来持つ味や香りを大切にし、栄養価が薄まらないように努めています。
一人ひとりに寄り添う栄養計画
必要に応じてONS(経口栄養補助)を適切に活用し、個々の患者様に最適な栄養状態をサポートします。
五感で味わう、彩りと香り
蓋を開けた瞬間の「わぁ」というときめきを大切にしています。メインのお皿では食材ごとにミキサーにかけるなど彩りよく盛り付け、ソースや出汁の香りがふわっと立ち上るように工夫しています。
目指すは、常食を超える本物の味
既製品を減らし手作りにこだわるのはもちろん、酵素や圧力鍋で常食と同じ味付けを実現。加水で味がぼやけないよう出汁の旨みを足すなど、繊細な調整を加えています。
心地よい、まとまりのある食感
歯茎でつぶせる柔らかきざみ食には「あんかけ」を活用してまとまりやすくしたり、お粥のベたつきを抑えたり、「食べやすくなった」と評価いただく食感を追求しています。
想いを込めたチームの味が、最高のスパイス
美味しい食事は、技術だけで生まれるものではありません。調理担当者が必ず味見を行い、自信をもってお届けできるものだけを提供。チーム一丸となって最高の美味しさを目指しています。

ボリュームが多くなりがちな嚥下調整食の栄養価を高め、おいしく食べられる工夫を込めた「栄養強化嚥下調整食」の導入事例を紹介します